スポーツイベントや地域活性化の町おこしイベントなどを行う時には
参加者が大きな声をあげるなどして、気合いを入れながら活動をしたり
質の良い物を提供したりすることも大切ではありますが、視覚的な効果も高めると
さらに盛り上がりが期待できるものです。
そして、この視覚的な効果に優れているアイテムなのが、のぼり旗です。
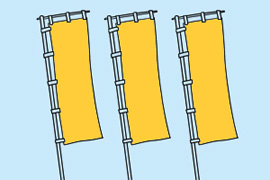
のぼり旗が風の力を受けてバタバタと動く姿というのは
活気があふれているイメージがあるもので、
得られる効用効果は素晴らしいものがあります。
イベント会場で使う場合、多いのが案内としてのぼり旗を設置することです。
初めてその場所に行く人も多いため、どこで何を開催しているかわからなくても
のぼり旗で示してくれたらすぐにわかりますし、親切心も感じられて好感が持てます。
また、風のない日はバタバタと動くことはなく、静かにゆったりと動く姿になりますが、
歌舞伎の公演や夜の屋台など、イベントの内容によってはこういった雰囲気が出せた方が盛り上がることもあるものです。
一方、多くの人が集まる場所にのぼり旗を設置する場合、危害を加えることのないよう
配慮もしておく必要があります。
夜に設置する場合は、暗くてデザインが見にくくなってしまったり
視認されにくくなってしまう可能性もありますので、
蛍光色や遮光生地などを利用して、目立つように工夫するのも良いでしょう。
このように、のぼり旗と言うのは、昼でも夜でも、また屋外だけでなく屋内においても
高揚感を高めることができる、とても優れたアイテムだと言えます。
なお、既製のデザインを使用するのも良いですが、
オリジナルのデザインや文字で作成して使用すると
かなり個性が出せて、大きな盛り上がりが
期待できるものです。
江戸時代に生まれた日本風書体「江戸文字」の特徴とメリット
歌舞伎の演目や役者の名前が書かれた看板などで良く見かける字体の「勘亭流」は、
江戸文字を総称する文字として知られています。
江戸時代の後期に書家の岡崎屋勘六が考案し、その屋号「勘亭」が名前の由来となりました。
江戸文字の特徴は、看板の文字が遠目からもはっきり見えるように
太く強調してデザインされた字体で、千客万来を願ってハネやはらいが
全て内側に向かって入るようになっており、枠いっぱいに隙間なく書かれているため、
別名を芝居文字とも呼ばれています。
江戸文字には他にも寄席文字や相撲文字、提灯文字などがありますが
何れも勘亭流から派生したもので、よく似ているものの使用される業界によって
字を詰まりぎみであったり、字面を厚く四角めの字体にしたりと
それぞれ細部が少しずつ異なっていることが特徴です。
パソコンのフォントにも登録されており、現在ではお茶や日本料理、温泉などの
「和風」をアピールしたい場合によく使用されています。
